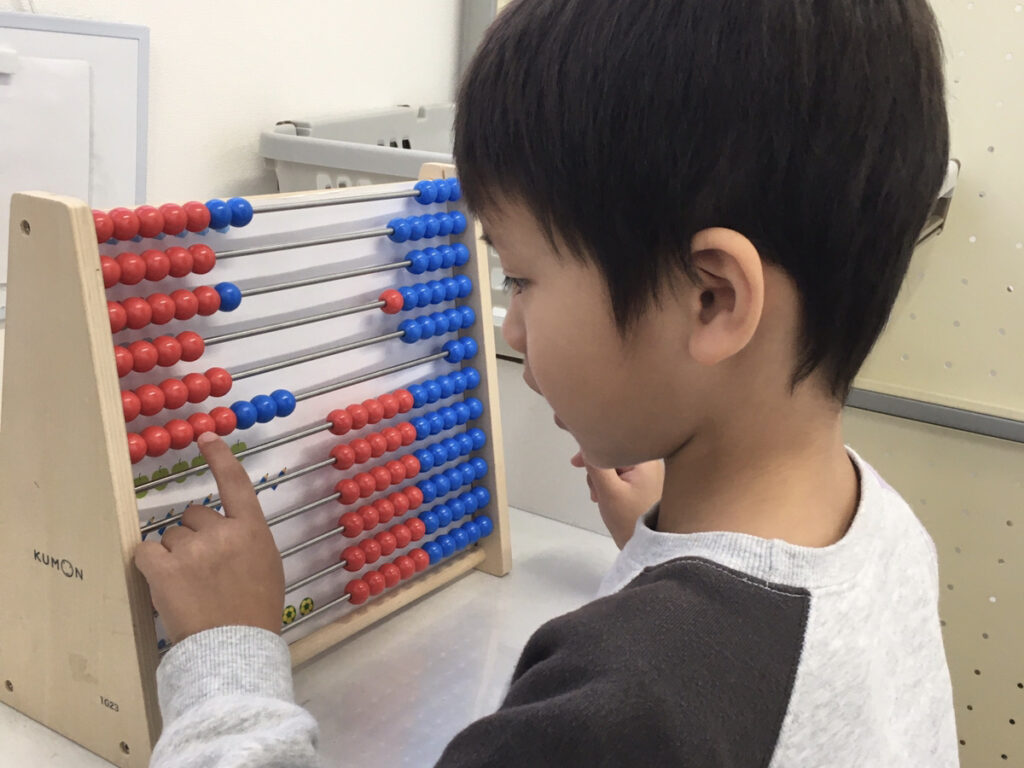融通が利かないASDの子どもにどう対応する?こだわりへの理解と対応のコツ
「一度決めたことを変えられない」「予定外のことが起きるとパニックになる」
そんなASD(自閉スペクトラム症)の特性に悩む保護者の声を、私たちゆめラボでは日々耳にします。
ASDのお子さまは、「予測できないこと」に強い不安を感じやすく、環境や予定の変化に対応することが難しい傾向があります。
このページでは、ASDの子どもが融通を利かせることが難しい理由と、日常生活や療育の場でできる具体的な対応方法についてご紹介します。
INDEX
ASDの子どもが「融通が利かない」と言われるのはなぜ?
ASDのお子さまが予定変更や臨機応変な行動に対応するのが難しいのには、脳の特性による明確な理由があります。
ここでは、代表的な3つの特性について解説します。
特性1:予測できない状況に強い不安を感じる
ASDの子どもは、見通しの立たない状況が苦手です。
「いつ」「どこで」「なにをするか」が明確でないと、不安や混乱を招きやすくなります。
特性2:思考の柔軟性が弱く、変更に適応しづらい
予定変更やルールの例外などに対応するには「柔軟な思考力」が必要ですが、ASDの子どもはこの分野の発達がゆっくりなことがあります。
特性3:こだわりが強く、独自のルールを持っている
「青いコップじゃないと嫌」「この順番で着替えたい」など、独自のルールがあることで融通が利かないように見えることもあります。
ご家庭でできる対応の工夫
家庭での日常生活の中でも、ASDの特性を踏まえた対応を意識することで、子どもの不安や混乱を大きく減らすことが可能です。
ほんの少しの工夫が、子どもにとっての「安心」につながり、スムーズな行動を引き出すきっかけになります。
以下のような対応を、できることから取り入れてみてください。
見通しを持てるように伝える
ASDのお子さまは、次に何が起こるかが分からないと、不安になったり行動が止まってしまうことがあります。
1日の流れをホワイトボードや絵カード、タイムスケジュール表などで「視覚的に」伝えることで、予測ができ、不安が軽減されやすくなります。
言葉だけでなく、目で見て分かる方法を使うことがポイントです。朝の準備、帰宅後の過ごし方、就寝前の流れなど、日常のルーティンを可視化することで、安心して行動しやすくなります。
変更を事前に知らせる習慣をつける
急な予定変更は、ASDの子どもにとって大きなストレスです。「今から〇〇するよ」と突然伝えるのではなく、事前に予告することで心の準備ができ、スムーズに行動に移りやすくなります。
たとえば、「あと5分したらお風呂にするよ」「おもちゃはあと1回で終わりだよ」など、時間の見通しや区切りを意識した声かけが効果的です。砂時計やタイマーなどのツールを活用するのもおすすめです。
「いつもと違う」ことを事前に練習しておく
イベントや旅行、来客などの「非日常的な出来事」はASDの子どもにとって大きな不安要素になりがちです。こうした状況に慣れるには、前もっての準備が欠かせません。
たとえば、「明日は知らない人が来るよ」「いつもと違う公園に行くよ」と事前に話しておいたり、写真や動画で場所の様子を見せたりしておくと、当日の不安を和らげる助けになります。
必要に応じて、事前にロールプレイや練習をしておくことも有効です。
療育での関わり方のポイント
児童発達支援の現場では、ASDのお子さまの特性に配慮しながら、少しずつ「変化に慣れる力」や「柔軟な思考」を育てていくことが重要です。
無理に変化を求めるのではなく、安心感を土台にしながら段階的にステップアップできるよう支援していきます。以下は、ゆめラボが日々の療育で大切にしている具体的な関わり方です。
選択肢を提示して安心感を得る
ASDの子どもにとって、「自分で選べること」は大きな安心につながります。
たとえば、「赤い鉛筆と青い鉛筆、どちらを使いたい?」や、「ブロック遊びとお絵かき、どっちを先にする?」など、選択肢を提示することで、本人の意志を尊重しながら活動に導くことができます。
選択肢はあらかじめ限定しておくことがポイントです。選択肢が多すぎると混乱してしまう場合もあるため、「2択」「3択」にとどめておくとスムーズです。
自分で選んだという感覚が自己決定感につながり、活動への参加意欲も高まります。
あえて小さな変更を経験させる
ASDの子どもは、日課や手順、ルールの「いつも通り」に強い安心を感じます。一方で、少しの変更にも強いストレスを感じやすいため、無理のない範囲で小さな変化を体験させることが、柔軟な対応力の獲得につながります。
たとえば、「おやつの時間に食べる場所をいつもと少し変える」「順番をほんの少し変える」「使う道具の色を変更する」など、子どもが気づくか気づかないかくらいの小さな違いから始めます。
そして、違和感や不安を感じたときは職員がすぐにフォローに入り、「大丈夫だよ」「先生と一緒だから安心していいよ」と安心感を伝えることで、徐々に変化への耐性を育てていきます。
ルールや流れに理由を伝える
ASDのお子さまの中には、「納得しないと行動に移せない」「理由がわからないと不安になる」という子が少なくありません。そのため、活動や変更に対しては必ず「理由」を丁寧に伝えることが大切です。
たとえば、「今日は雨だからお外遊びはお休みで、お部屋で風船遊びにしようね」など、なぜ変更が必要なのかをわかりやすい言葉で説明します。
理由を説明することで、子ども自身が納得しやすくなり、見通しが持てるようになります。
また、理由を伝える習慣がつくことで、子どもも「ルールには意味がある」と理解しやすくなり、先々の集団生活への適応力にもつながります。
まとめ:特性を理解し、少しずつ「変化に慣れる力」を育てましょう
ASDのお子さまにとって、柔軟な対応を求められる場面は大きなストレスになります。
だからこそ、日々の生活や療育の中で「見通しを持てる工夫」や「段階的な慣れ」を積み重ねることが大切です。
私たち児童発達支援事業所ゆめラボでは、お子さま一人ひとりの特性を見極めながら、「こだわり」と上手につきあうための支援を行っています。「融通が利かない」と感じる行動の背景には、必ず理由があります。
ご家庭での悩みや困りごとも、ぜひゆめラボにご相談ください。
📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)
📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/
💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw
各教室の情報が満載!
公式SNS




お問い合わせ
お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら
お悩みなど、お気軽にご相談ください